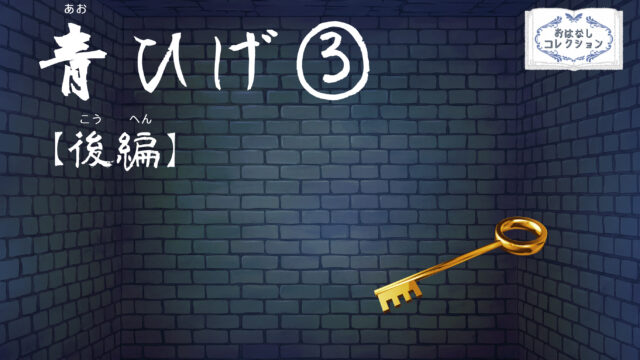青ひげを持つ男の恐ろしい正体を知った娘の話②


- 怖い話は得意。
- 怖い話が好きな子ども(年長)に読み聞かせしたい。
このおはなしの作者
※名前をクリックすると別ウィンドウでWikipediaの作者情報が表示されます。
前回までのあらすじ

おはなしの始まりはここから
★この文章は3分で読めます
すると、奥方の知りあいや、お友だちは、お使いを待つ間も、もどかしがって、我先に集まって来ました。
お嫁入り先の、立派な住まいの様子が、どんなだか、どのくらい、みんなは見たがっていたでしょう。
ただ主人が家にいる時は、例の青ひげが怖くて、誰も寄りつけなかったのでございます。
みんなは、居間、客間、大広間から、小部屋、衣装部屋と、片っぱしから見て歩きましたが、いよいよ奥深く見て行くほど、だんだん立派にも、綺麗にもなっていくようでした。
とうとうお終いに、いっぱい家具のつまった、大きな部屋に来ました。
そのなかの道具や置き物は、この屋敷の内でも、一等立派な物でした。
壁掛けでも、寝台でも、長椅子でも、箪笥でも、机や、椅子でも、頭のてっぺんから、足の爪先まで映る姿見でも、それはむやみに沢山あって、むやみにぴかぴか光って、綺麗なので、誰も彼も、ただもう感心して、ふうと、ため息をつくだけでした。
姿見の中には、水晶の縁の付いたものもありました。
金銀めっきの縁の付いたものもありました。
何もかも、この上もなく結構ずくめな物ばかりでした。
お客たちは、まさかこれほどまでとも思わなかった、お友だちの運の良さに、いまさら感心したり、羨ましがったり、いつまでも果てしがありませんでしたが、ご主人の奥方は、いくら立派なお部屋や、飾り付けを見て歩いても、じれったいばかりで、一向におもしろくも楽しくもありませんでした。
それというのが、夫が出掛けに厳しく言いつけておいていった、地下室の秘密の小部屋というのが、始終、どうも気になって気になって、ならないからでございます。
いけないと言うものは、とかく見たいのが、人間のくせですから、そのうちいよいよ、我慢がしきれなくなってくると、この奥方は、もうお客に対して、失礼のなんのということを、思ってはいられなくなって、ひとりそっと裏梯子を下りて、二度も三度も、首の骨が折れたかと思うほど、はげしく、柱や梁にぶつかりながら、夢中で駆け出して行きました。
でも、いよいよ小部屋の戸の前に立ってみると、さすがに夫の厳しい言いつけを、はっと思い出しました。
それに背いたら、どんな不幸せな目にあうかしれない、そう思って、しばらくためらいました。
でも、誘いの手が、ぐんぐん強く引っ張るので、それをはらいきることは、できませんでした。
そこで、小さい鍵を手に取って、ぶるぶる震えながら、小部屋の戸を開けました。
窓が閉まっているので、はじめはなんにも見えませんでした。
そのうち、だんだん、暗闇に目が慣れてくると、どうでしょう、そこの床の上には、いっぱい血の塊がこびりついていて、五六人の女の死骸を、並べて壁に立てかけたのが、血の上に映って見えていました。
これは、みんな青ひげが、ひとりひとり、結婚した後で殺してしまった女たちの死骸でした。
これを見たとたん、奥方は、あっと言ったなり、息が止まって、身がすくんで動けなくなりました。
そうして、戸の鍵穴から抜いて、手に持っていた鍵が、いつか、すべり落ちたのも知らずにいたくらいです。
しばらくして、やっと我に返ると、奥方は慌てて、鍵を拾い上げて、戸を閉めて、急いで二階の居間に駆けて帰ると、ほっと息をつきました。
でも、いつまでも胸がどきどきして、正気に戻れないようでした。
見ると、鍵に血が付いているので、二三度、それを拭いて取ろうとしましたが、どうしても血が取れません。
水につけて洗ってみても、石けんと磨き砂をつけて、砥石でごしごし擦ってみても、一向に取れる気配はありません。
血の付いた跡は、いよいよ濃くなるばかりでした。
それもそのはず、この鍵は魔法の鍵だったのです。
ですから、表側の方の血を落としたかと思うと、それは裏側にいつの間にか余計濃く、滲み出していました。

読了ワーク
思い出してみよう
- ご主人の奥方は、部屋にある沢山の綺麗な物を見て歩いても、楽しいとは思えませんでした。それはどうしてでしょうか。
- 小部屋の鍵に付いた血は何をしても取れませんでした。それはなぜでしょうか。
調べてみよう
- “梁”とは何でしょうか。
- 『跡』と『痕』の違いは何でしょうか。


単語ピックアップ
1.感心(かんしん)
(立派なものや綺麗なものを見て)心を動かされること。
2.正気(しょうき)
確かな意識があること
3.砥石(といし)
物を磨くための道具
音読シートダウンロード
★この物語“青ひげ②【中編】”の音読シートがダウンロードできます。
[download id=”1948″]
読了ワーク『思い出してみよう』の解答例
- 地下室の秘密の小部屋のことが気になって仕方がなかったから。
- 魔法の鍵だったから。